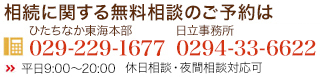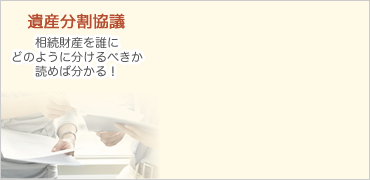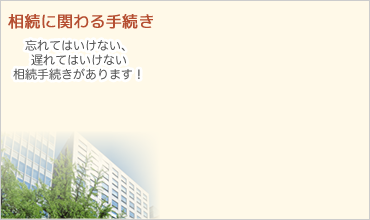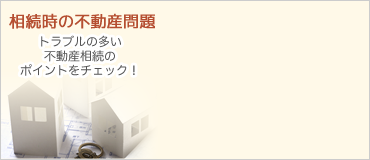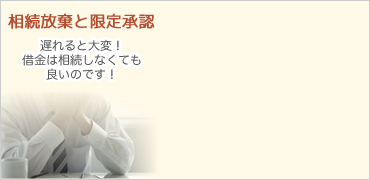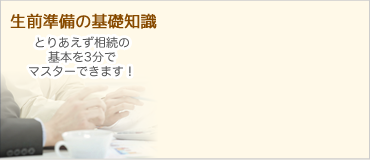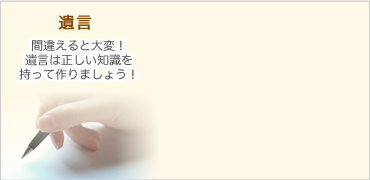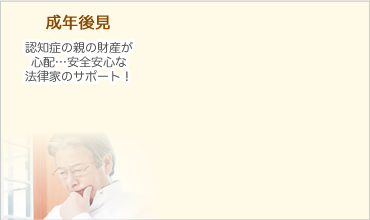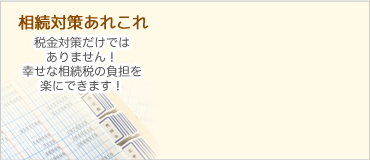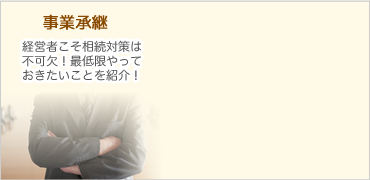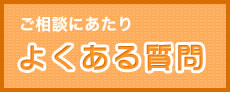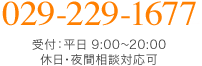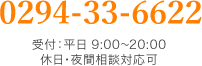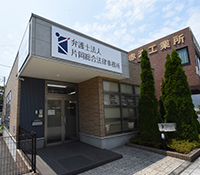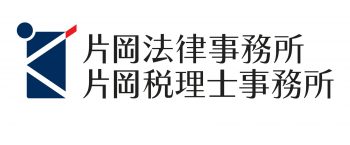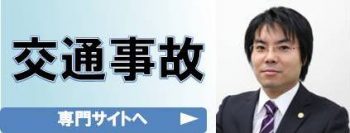夫婦間の財産移動、落とし穴にご注意!賢い資産管理術とは?
当事務所がYouTubeで公開した動画「夫婦間贈与の落とし穴と賢い財産移動術」の内容を基に、夫婦間での財産のやり取りに関する重要な注意点と、賢くスムーズに財産を移動させる方法について解説します。
夫婦間では財布が一緒というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、法律上はあくまで別々の個人として扱われます。そのため、安易な財産の移動は思わぬ税金の問題を引き起こす可能性があります。
1. 夫婦間の財産移動に「贈与税」がかかるのはなぜ?
夫婦間であっても、お金の移動があれば基本的には「贈与」とみなされ、一定の金額を超えると贈与税が発生する可能性があります。
特に贈与税が問題になりやすいのは、以下のような「不動産」が絡むケースです。
不動産の名義を配偶者に移す場合。
家を購入する際に、夫(または妻)が全額を出したにもかかわらず、夫婦の共有名義(例:1/2ずつ)にしてしまう場合。
2. 贈与税は「いつ」「どのように」バレる?
「夫婦間のことだからバレないだろう」と考えて放置していると、後で大きな問題に発展することがあります。贈与税が発覚する主なタイミングは以下の通りです。不動産の名義変更時:名義変更の情報は国の機関に届くため、そのタイミングで把握されることがあります。
財産債務調書制度
多額の財産を持つ人が提出義務を負う「財産債務調書制度」を提出している場合、財産の大きな変動があった際にすぐに把握されやすくなります。
相続税の税務調査時
最も注意が必要なのがこのケースです。贈与から10年後、20年後、あるいはそれ以上の期間が経ってから、配偶者が亡くなった際の相続税の税務調査で贈与の漏れを指摘されることがよくあります。たとえば、亡くなる6年以内に行われた贈与は、相続税の調査で贈与税の申告漏れとして指摘される可能性があります。
3. 夫婦間の不動産名義変更の注意点
夫婦間で不動産の名義を変更すること自体は可能です。売買、贈与、あるいは離婚時の財産分与といった形が考えられます。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
落とし穴①:「20年以上の夫婦間の贈与の特例」を使っても申告は必要!
「結婚して20年以上連れ添った夫婦であれば、不動産の名義変更をしても贈与税がかからない制度がある」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは「居住用不動産の贈与税の配偶者控除の特例」という制度のことで、正しく適用すれば贈与税はかかりません。
しかし、この特例を適用するためには、たとえ税金がかからなくても「贈与税の申告」が必須です。この申告を怠ると、特例が適用されず、純粋に贈与税が発生し、さらに延滞金などのペナルティが課されることになります。
【ここがポイント!】 「基本的に税金がかかるが、例外的にかからない」という制度を使う場合は、必ず「申請(=申告)」が必要であると覚えておきましょう。
落とし穴②:離婚時の財産分与と贈与税
離婚時の財産分与で名義変更を行う場合、適正な範囲内であれば贈与税はかかりません。例えば、夫婦が結婚後に築き上げた財産を、配偶者の貢献度に応じて適切に(例えば1/2程度に)分与するようなケースです。
この場合は原則として贈与税はかからず、申告も不要です。ただし、過度に財産を渡しすぎた場合は、その超えた部分に贈与税がかかる可能性があり、その際には申告が必要となる場合があります。
4. 賢い財産移動術と考えるべき視点
夫婦間の財産移動を考える際、目先の自分たちの財産だけでなく、より広い視点を持つことが非常に重要です。
視点①:将来の相続まで見据える
「旦那さんの方が財産が多いから、奥さんに移しておこう」と考えがちですが、奥さんのご両親の財産や、お子さんのいないご兄弟の財産など、将来的に奥さんに入ってくる可能性のある財産まで含めて考えることで、どちらの財産が多くなるかという見方が変わってきます。
このように、自分たち夫婦の世代だけでなく、2世代先のことまで含めて広い視野で相続対策を行うことが望ましいとされています。
視点②:不動産の名義変更以外の方法も検討する
配偶者に不動産を名義移転する以外にも、以下のような選択肢があります。
名義移転をしない(現状維持):かつては相続登記をせずにそのままにすることがありましたが、現在は相続登記の義務化が始まっており、この方法は推奨されません。
配偶者居住権の設定:夫(または妻)が亡くなった際、不動産の名義はお子さんに移しても、残された配偶者がその家に住み続ける権利だけを確保する制度です。相続税の節税にも繋がり得るメリットがあります。
視点③:贈与税をかけずにシンプルに財産を移動させる方法
毎年贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内で少しずつ現金を移す方法もありますが、銀行振込の手間などを考えると面倒に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、よりシンプルで効果的な方法として、「家計の生活費の負担割合を調整する」という方法があります。
例えば、夫と妻にそれぞれ収入がある場合でも、夫が光熱費や携帯代など、生活費の大部分を負担するようにします。これにより、妻の財産は減らず、結果として妻の財産が増える(または減らない)形となり、実質的な財産移動につながります。
これは、共働きの場合でも、年金生活の場合でも有効です。どちらか一方に財産が偏りすぎないように調整することが重要です。生活に必要な費用を、一方の配偶者が負担することは贈与税の対象とならないため、合法的な節税対策となります。
まとめ
夫婦間の財産移動は、一見シンプルに見えても多くの注意点や落とし穴が存在します。今回の記事でご紹介したように、安易な名義変更や財産移動は思わぬ贈与税やペナルティに繋がりかねません。
また、財産移動を考える際には、ご夫婦の現在の財産だけでなく、将来の相続まで見据えた広い視野で、多角的に検討することが重要です。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な財産移動や相続対策について、専門家が丁寧にアドバイスを行っております。夫婦間の財産に関するご不安やご質問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします! コメントやLINEでのご相談も受け付けております。