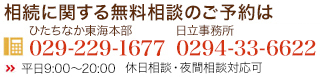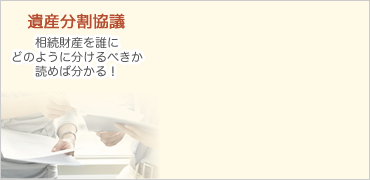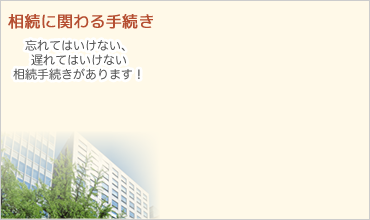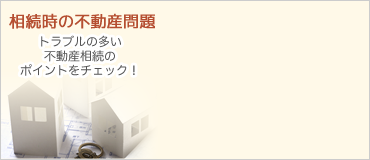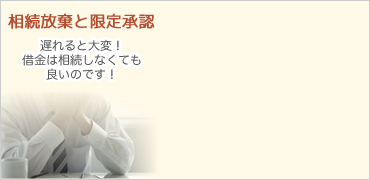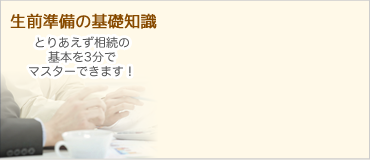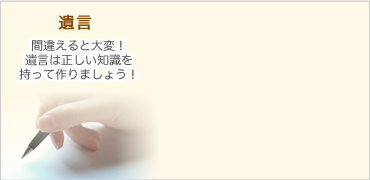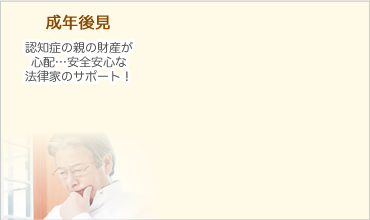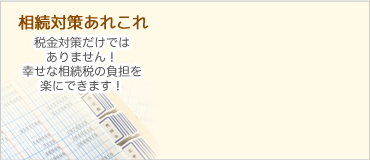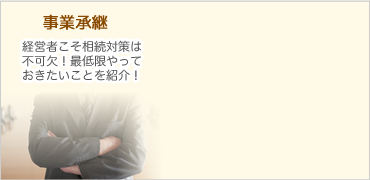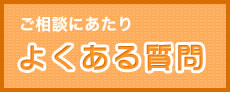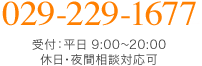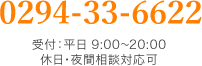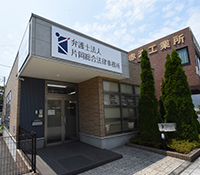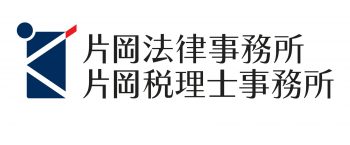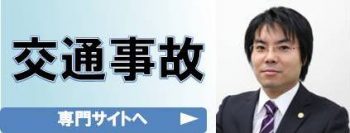【税理士が語る 生前贈与の落とし穴】失敗しないための注意点と対策
当事務所のYouTubeチャンネルで公開した動画「税理士が語る 生前贈与の落とし穴」はご覧いただけましたでしょうか? 今回は、動画の内容を抜粋し、生前贈与を検討されている方が陥りがちな「落とし穴」とその具体的な対策について、ウェブ記事として詳しくご紹介します。
生前贈与は、相続税対策として有効な手段の一つですが、正しい知識と適切な手続きがなければ、税務署とのトラブルに発展し、かえって大きなペナルティを課される可能性があります。ご自身の資産を次の世代へスムーズに引き継ぐために、ぜひご一読ください。
最も避けるべき「贈与税申告をしない」ことの危険性
生前贈与において、最もやってはいけないのが「贈与税申告をしないこと」です。年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要です。
「少額だからバレないだろう」と考えている方もいるかもしれませんが、税務署は贈与者が亡くなった際の相続税調査において、過去10年、あるいはそれ以上の期間にわたる金融機関の動きを徹底的に調査します。この調査は、贈与者本人だけでなく、お子さんやお孫さんの通帳・口座まで広範囲に及ぶため、マイナンバーの紐付けがなくても把握されてしまいます。多額の資金移動があれば、その出所が必ず問われ、不適切な贈与と判断されれば、数年後に追徴課税やペナルティを受ける可能性があります。
基礎控除内で賢く贈与するための工夫
年間110万円の基礎控除を最大限に活用し、贈与税をかけずに資産を移転する方法も存在します。
渡す人を増やす工夫
例えば、親が子に300万円を贈与すると贈与税申告が必要ですが、その子と配偶者、さらに子2人にそれぞれ110万円ずつ贈与すれば、合計440万円まで非課税で贈与が可能です。1人あたり110万円の基礎控除があるため、贈与する人数を増やすことで全体の非課税枠を広げることができます。
贈与相手の人数に制限はない
原則として、110万円の基礎控除は受け取る側にかかるため、人数に上限はありません。しかし、常識的に考えて、お世話になっている人や親族など、関係性のある相手に贈与することが前提となります。
最も注意すべき「名義預金」とは?
「名義預金」は、生前贈与の失敗例として最も多く見られるケースの一つです。
名義預金とは
名義は他の人の預金口座であるにもかかわらず、実際にはその名義人とは別の人が財産を所有していると見なされる預金のことです。例えば、おばあちゃんがお孫さんの名義で口座を作り、その通帳をずっとおばあちゃんが預かっているようなケースが該当します。
名義預金と判断されないための対策
税務署から名義預金と指摘されないためには、以下の点を徹底する必要があります。
- 印鑑を各自で用意する: 贈与する側とされる側で、それぞれ異なる印鑑を使用することが重要です。印鑑が同じでは、贈与が成立していないと疑われます。
- 預金口座は名義人の居住地に近い金融機関で作成する: 例えば、贈与する側が鹿児島、受け取る側が東京に住んでいる場合、受け取る側が使用するはずのない鹿児島の口座で預金をするのは不適切なケースです。
- 通帳・キャッシュカードは名義人が管理する: 贈与された預金は、名義人が自由に処分できる状態でなければなりません。通帳を贈与した側が預かり、名義人が一切使用していない場合は名義預金と判断されます。
- 預金の使用実績を作る: 定期的に預金を引き出したり、何か支払いに充てたりして、名義人が口座を「使っている」実態を記録に残すことが安全です。
- 名義人本人の日常使いの口座に振り込む: 最も確実な方法は、贈与された人が普段利用している金融機関の口座、例えばアルバイトの給与振込口座などに直接振り込むことです。
「タンス預金」を生前贈与するリスク
いわゆる「タンス預金」(自宅に現金を保管すること)を生前贈与しようとすることも、トラブルの元となります。
- 出所の不明確さ: タンス預金は、そのお金が誰のもので、どこから来たのかが不明確になりがちです。これにより、税務署と揉める原因となります。
- 相続時のリスク: 贈与者が亡くなった際にタンス預金があると、相続人がその存在を隠してしまい、後に税務署にバレて大きなペナルティを受ける可能性があります。
- 推奨されない: 税務署との無用なトラブルを避けるためにも、タンス預金による生前贈与は推奨されません。
- 既存のタンス預金への対処法: すでにタンス預金がある場合は、できるだけ使用して減らすか、金融機関に入金することが無難です。
「贈与契約書」の重要性と作成ポイント
贈与を適法に行う上で、「贈与契約書」は重要な役割を果たします。
贈与契約書とは
贈与契約書とは、贈与する人と受け取る人の間で、「いつ、いくらを渡すか」を明確にした契約書です。不動産の賃貸借契約書のように、双方の署名(またはサイン)が必要です。
作成のポイント
-
決まった様式はない
- 贈与契約書に特定の決まった形式はありません。内容が明確であれば、Wordなどで作成し、双方の署名があれば有効です。LINEなどのメッセージであっても、贈与の意思と合意が確認できれば、一種の証拠となり得ます。
-
毎年の作成が望ましい
- 贈与契約書は、毎年作成するのが望ましいです。特に、1000万円を10年間にわたって贈与する計画がある場合など、まとまった金額を分割して贈与するケースでは、毎年その年の贈与の意思決定と合意を示すことで、一括贈与と見なされ、まとめて課税されるリスクを避けることができます。
-
-
注意点
- 複数年分の契約書をまとめて作成することは避けてください。日付や使用するペンのインクなどから、一括作成と判断される可能性があります。
-
-
未成年者への贈与では必須
- お子さんやお孫さんなど、小さなお子さん(5歳や10歳など)に贈与する場合、贈与契約書はほぼ必須と考えてください。
-
-
署名方法
- 未成年者は自身でサインができないため、贈与を受ける側の親権者(通常は両親、一人でも可)が、親権者として代理で署名します。
-
本人がサインできる年齢
- 18歳以上であれば本人がサインすべきです。17歳や16歳でも少額でアルバイトができる年齢であれば本人サインも考えられますが、原則として18歳未満の場合は親権者のサインがより安全です。
-
-
作成のメリット
- 不動産贈与と異なり、お金がかからず無料で作成できるため、安心感を得るためにも作成を推奨します。
不適切な贈与が発覚した場合の「税務調査」の負担
もし不適切な贈与を行ってしまい、税務署から指摘を受けることになれば、贈与者が亡くなった後の相続税申告から3~5年後に税務調査が入ることがあります。税務調査では、自宅での聞き取りや書類の確認が3日間ほどにわたって行われるなど、精神的な負担が非常に大きいものです。
このような状況を避けるためにも、ご紹介した注意点を一つ一つ確認し、失敗しない生前贈与を実践することが非常に重要です。
生前贈与は、適切な手続きを踏めば非常に有効な資産承継の手段となります。しかし、誤った認識や手続きは、予期せぬトラブルや大きな負担を招く可能性があります。
当事務所では、生前贈与や相続に関するご相談を随時受け付けております。ご自身のケースに合わせた具体的なアドバイスをご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。