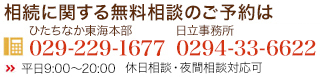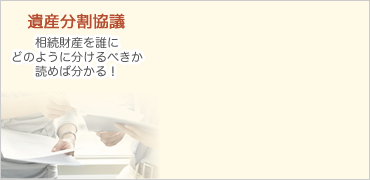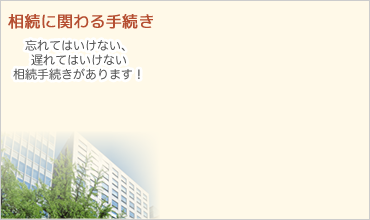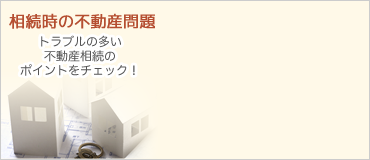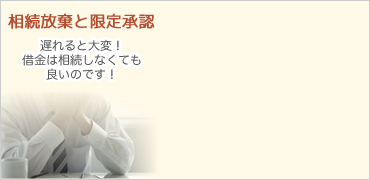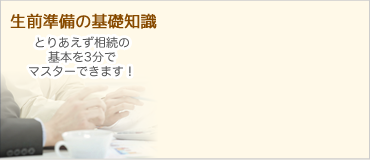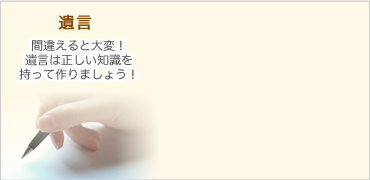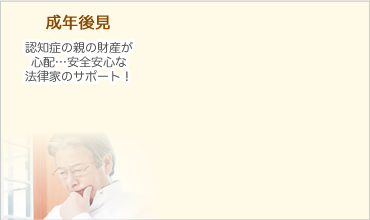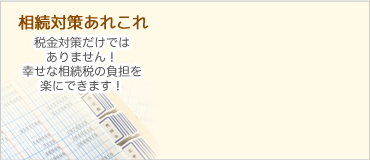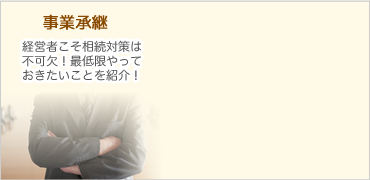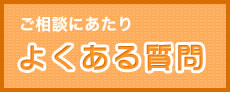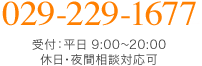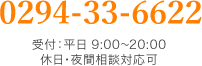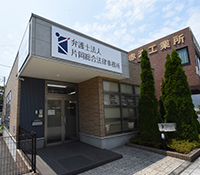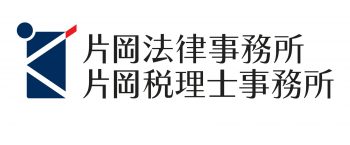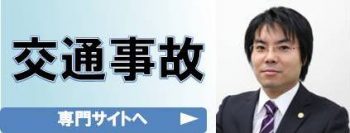【最新情報】2024年改正 相続時精算課税制度を徹底解説!生前贈与で賢く節税するポイントと心構え
当事務所のYouTubeチャンネルで公開した動画「【2025年最新版】改正後の相続時精算課税がこう変わる!知らないと損するポイントを税理士が解説」の内容を基に、2024年に改正された相続時精算課税制度の変更点、活用メリット、そして注意点について詳しく解説します。単に税金を減らすだけでなく、ご家族の幸せに繋がる「お金の渡し方」についても考察します。
1. 改正前の相続時精算課税制度とは?:現金贈与には不向きだった理由
まず、2024年の改正前の相続時精算課税制度の概要からご説明します。 この制度は、生前に贈与した財産については贈与税がかからないものの、贈与した金額を相続時に相続財産に加えて相続税を計算する、というものでした。つまり、**「納税の先送り」**という性質が強く、現金のようにそれ自体が増えるわけではない財産にはあまり使われていませんでした。主に、将来値上がりが見込まれる不動産や収益を生む株式などの贈与に活用されることが多かったのです。
2. 2024年改正のポイント:現金贈与が有利に!
今回の改正で、相続時精算課税制度は大きく変化し、現金贈与においても非常に有効な選択肢となりました。
- 110万円の基礎控除が新設:
- 従来の「歴年贈与(年間110万円の非課税枠)」はそのまま存続します。
- これに加えて、相続時精算課税制度を選択した場合に、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。
- この110万円の基礎控除は、相続発生時に相続財産に加算されることがありません。つまり、「納税の先送り」ではなく、**完全に贈与税・相続税が非課税となる「非課税枠」**として機能します。
- 歴年贈与との併用で年間220万円まで非課税に!:
- 今回の改正により、例えば「父から子へ歴年贈与で110万円」と、「母から子へ相続時精算課税制度を適用して110万円」という形で贈与を行うことで、子1人あたり年間合計220万円まで贈与税・相続税を課されることなく贈与することが可能になりました。
- この年間110万円の基礎控除に、年数の上限はありません。極端な話、小さい頃から毎年ずっと贈与を続けることも可能です。
3. 改正された制度の注意点
非常にメリットの大きい改正ですが、いくつか注意すべき点があります。
- 一度選択すると歴年贈与には戻れない: 相続時精算課税制度を一度選択して届出を提出すると、その贈与者(お金を渡す側)は、後から歴年贈与(従来の110万円控除)に制度を切り替えることはできません。慎重な検討が必要です。
- 同一の贈与者は両制度を併用できない: 例えば、父親が「歴年贈与」と「相続時精算課税制度」の両方を同時に使って贈与することは認められません。年間220万円の非課税枠を活用するには、父親が歴年贈与を、母親が相続時精算課税制度を利用するなど、異なる贈与者から贈与を受ける必要があります。
- 夫婦間贈与を活用する際の注意点: 「父親に預金がたくさんあるが、母親には預金がない」というケースで、父親から母親に贈与し、そのお金を母親が相続時精算課税制度を使って子に贈与するという「テクニック」も考えられます。しかし、単に母親を経由させるだけでは、実質的に父親から子への贈与と見なされる可能性があります。このような「合わせ技」を検討する際は、必ず専門家にご相談ください。
- 受贈者(受け取る側)の要件が異なる:
- 歴年贈与: お子さんやお孫さんだけでなく、お子さんの配偶者なども対象にでき、受贈者の年齢制限もありません(未成年でも可能)。
- 相続時精算課税制度: 要件が限定されており、受贈者は贈与者の子または孫で、18歳以上である必要があります。
4. こんな方におすすめ!
今回の改正で、相続時精算課税制度と歴年贈与の併用は特に以下のような方におすすめです。
- 生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)をすでに使い切っている方。
- 多額のキャッシュ(現金預金)を保有しており、生前に計画的に贈与を進めたい方。
- 余命が限られており、数年間の間にまとまった金額を贈与したい方。
5. 税金だけじゃない「お金の渡し方」の哲学
単に相続税を節税するだけでなく、贈与を通じて家族関係を円滑にし、真の幸せを育むことも重要だと当事務所では考えております。
- 「限界効用逓減の法則」: 毎年決まった金額(例えば220万円)を機械的に贈与し続けると、最初のうちは喜ばれるかもしれませんが、そのうち「当たり前」と感じられ、感謝や喜びといった「満足度」は徐々に低下してしまうかもしれません。
- 「感謝が増える渡し方」を考える: 親としては見返りを求めているわけではないものの、「ありがとう」という感謝や円滑な人間関係を望むのは自然なことです。単に銀行振込で済ませるだけでなく、以下のような「お金の渡し方」を工夫することで、贈与の価値を高めることができるでしょう。
- お子さんが車を欲しがっている時に、車の購入費用を援助する(贈与税がかかっても、喜びは大きいかもしれません)。
- お子さんに子供が生まれた際、高価なベビーカーを贈るなど、お祝いとして必要な時に多めにお金を渡す。
- 「本当に必要なもの、その時に必要なものを渡す」。
このように、贈与は単なる節税対策に留まらず、家族の絆を深め、より豊かな人生を送るための手段となり得ます。
まとめ
2024年の改正により、相続時精算課税制度は生前贈与の選択肢として、これまで以上に注目すべき制度となりました。特に現金預金による贈与を検討されている方にとっては、年間220万円まで非課税で贈与できるというメリットは非常に大きいでしょう。
しかし、制度の活用には専門的な知識が必要であり、個々の家族構成や財産状況に合わせた最適なプランニングが不可欠です。また、単に税金を減らすだけでなく、贈与を通じて家族の絆を深め、幸せを育むという視点も忘れてはなりません。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況を詳細にお伺いし、最適な相続対策プランをご提案いたします。生前贈与や相続時精算課税制度についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この解説記事がお役に立った方は、ぜひ当事務所のYouTubeチャンネルをご覧いただき、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします! コメントやLINEでのご相談も受け付けております。