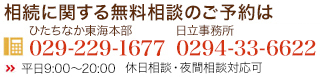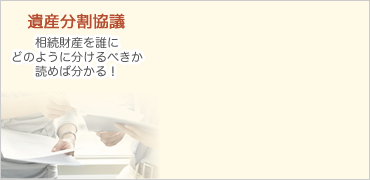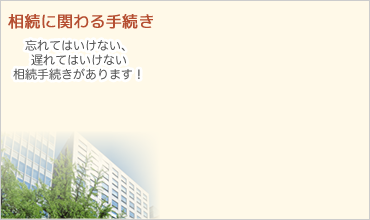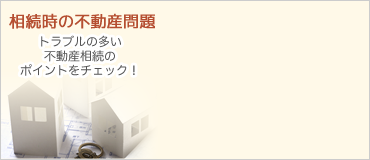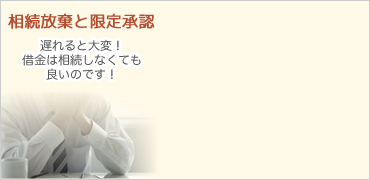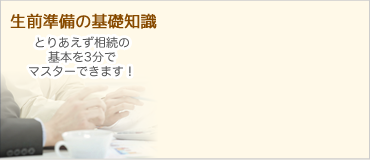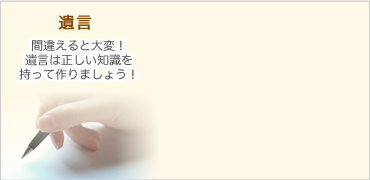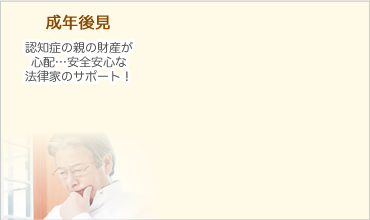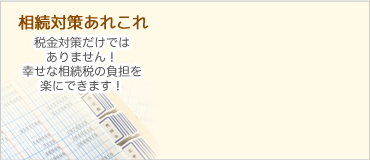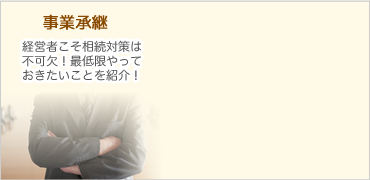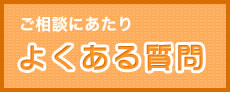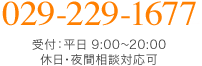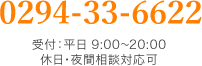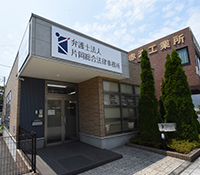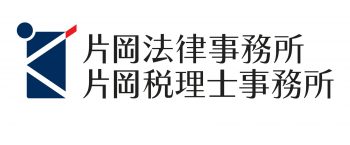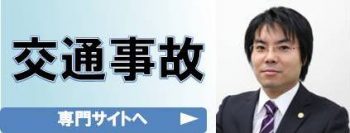生命保険で賢く節税! 相続対策の基本と落とし穴
「相続対策に生命保険が有効」と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、ただ加入すれば良いというわけではありません。当事務所のYouTubeチャンネルで公開した動画「税理士が教える!生命保険を活用した相続税対策の成功事例と失敗事例とは?」の内容を基に、生命保険を相続対策に活用する際のポイントや注意点について、専門的な視点から分かりやすく解説します。
1. 相続税対策に有効な生命保険の種類
生命保険には大きく分けて二つの種類がありますが、相続税対策として有効なのは、**「契約者が被保険者となり、その方が亡くなった時に保険金が支払われる一般的な生命保険」**です。この場合、受け取り人が相続人であれば相続税対策の対象となります。
一方で、契約者が子供などを被保険者として加入する生命保険は、相続における税金対策としては対象とならないことが多い点に注意が必要です。
2. 加入年齢や健康状態に関する実情
「年配になったら生命保険には入れないのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、実際には90歳近くまで加入できる生命保険は多く存在します。さらに、病気がある方でも加入できる保険も少なくありません。
これは、相続対策として活用される生命保険の多くが、保険料を「一括」で支払うタイプであるためです。例えば、500万円を一括で支払う場合、保険会社から見ればリスクがほとんどないため、高齢の方や病気をお持ちの方でも加入できる商品が多く開発されています。
ただし、認知症の程度によっては契約の意思確認が難しくなり、加入できないケースもあります。保険会社によっては担当者以外に上司が同行して意思確認を行うなど、慎重な手続きが求められるため、加入を検討する際は保険会社に直接確認することが重要です。
3. 生命保険活用の最大のメリット:非課税枠の活用
生命保険を相続対策として活用する最大のメリットは、現金で保有している場合とは異なり、相続税の非課税枠が適用される点です。
具体的には、「500万円 × 法定相続人の数」までは、相続税が非課税になります。 例えば、亡くなった方(被相続人)に配偶者と子供が2人いる場合、法定相続人は3人となるため、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税枠として利用できます。
この非課税枠は、受け取り人である相続人が誰か一人で全額を受け取っても良いですし、複数人で分け合っても構いません。また、この非課税枠は、通常の相続税の基礎控除とは別に適用されるため、非常に大きな節税効果が期待できます。
4. 保険金受け取り人の指定と留意点
生命保険の契約時に保険金受け取り人を指定しますが、一度指定するとその後の変更は難しく、変更した場合に贈与と見なされる可能性もあります。そのため、契約時には受け取り人を慎重に設定することが重要です。
相続税対策の観点から見た場合、純粋な相続税額を減らす目的であれば、配偶者よりもお子さんを受け取り人に指定する方がメリットが大きいケースが多いです。これは、配偶者には「配偶者の税額軽減の特例」という非常に大きな非課税枠があるため、生命保険の非課税枠はお子さんの相続分に充てた方が、全体としての節税効果が高まる傾向にあるためです。
5. 非課税枠を増やす「裏技」:養子縁組
「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠の「500万円」を増やす方法はありませんが、**「法定相続人の数」を増やす「裏技」**があります。
それは、養子縁組です。例えば、お子さんの配偶者を養子に迎えることで、法定相続人が一人増え、それに伴い生命保険の非課税枠も500万円増やすことが可能になります。養子縁組をしても実親との関係がなくなるわけではなく、戸籍上の手続きだけで非課税枠を増やすことができます。
6. 生命保険活用のその他のメリット
生命保険を活用するメリットは、相続税の節税だけではありません。
-
すぐに現金化できる
- 預貯金は相続人全員による遺産分割協議が必要で、実印や印鑑証明書を揃えるのに時間がかかりますが、生命保険は指定された受け取り人がすぐに請求できるため、約1週間から1ヶ月程度で現金を受け取ることが可能です。これにより、葬儀費用や納税資金、税理士報酬など、亡くなった直後に必要となる資金を円滑に確保できます。
-
遺産分割トラブルの軽減(「隠れた遺言」の性質)
- 生命保険金は、原則として遺産分割協議の対象となる相続財産から除外されます。そのため、「特定の相続人に多めに渡したい」といった故人の希望を、遺産分割に影響を与えることなく実現できます。これは「隠れた遺言」のような性質を持ち、相続人間での紛争を避ける一助にもなります。
-
プライバシーの確保(相続税申告が不要な場合)
- 相続税の申告が必要な場合は、保険金の受取状況も記載されるため、他の相続人に知られることになりますが、相続税の申告が不要な場合には、預金のように遺産分割の話し合いで分ける必要がないため、他の相続人に知られることなく保険金を受け取れるケースもあります。
7. 生命保険活用における最大の「落とし穴」:リビングニーズ特約
生命保険を活用する上で、最も注意すべき「落とし穴」の一つが、「リビングニーズ特約」です。
多くの生命保険に付帯されているこの特約は、被保険者が余命宣告を受けた場合に、生前に保険金を受け取ることができる制度です。これは一見すると良い制度に思えますが、相続税対策として生命保険を活用している場合には大きな問題となります。
なぜなら、生命保険の相続税非課税枠は、「被保険者が亡くなった時に、相続人が保険金を受け取った場合」にのみ適用されるためです。もし被保険者本人が生前にリビングニーズ特約を利用して保険金を受け取ってしまうと、そのお金は被保険者の預貯金となり、相続時には通常の相続財産として扱われ、せっかくの非課税枠が適用されなくなってしまいます。
重篤な病気の告知を受けた際に、入院費用などを賄うために安易にこの特約を利用してしまい、結果的に相続税対策が台無しになってしまうケースが少なくありません。生命保険を相続対策として加入している方は、この特約の利用には細心の注意が必要です。
8. 対策「完了」の勘違いと家族全体での検討の重要性
「非課税枠分(例えば1,500万円)の生命保険に入ったから、相続対策はもう完了だ」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には、配偶者の方の将来的な資産状況も考慮に入れる必要があります。
配偶者がご自身の親御さんやご兄弟から財産を相続する可能性、あるいは先に亡くなった配偶者から財産を受け取ることで、将来的に配偶者自身が大きな資産を保有する「資産家」となるケースも考えられます。その場合、配偶者が亡くなった際の相続対策も視野に入れ、配偶者自身も生命保険に加入しておくメリットがあります。
「配偶者に手元資金がないのにどうやって保険料を払うのか?」という疑問に対しては、生前贈与や相続時精算課税制度を活用して資金を移転し、その資金で保険料を一括払いしたり、数年かけて計画的に保険に加入していくといった方法があります。
まとめ
生命保険を活用した相続対策は、単純なようでいて、税法上の特例や個々の家族状況に応じたきめ細やかな計画が不可欠です。安易な判断は、思わぬ落とし穴にはまってしまうリスクも伴います。
当事務所では、お客様それぞれの状況を詳細にお伺いし、生命保険を始めとする最適な相続対策プランをご提案いたします。ご自身やご家族全体の財産状況を見据え、長期的な視点での相続対策をご検討される方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この解説記事がお役に立った方は、ぜひ当事務所のYouTubeチャンネルをご覧いただき、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします! コメントやLINEでのご相談も受け付けております。