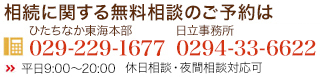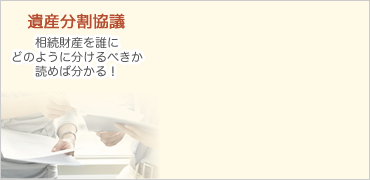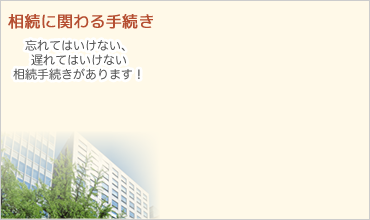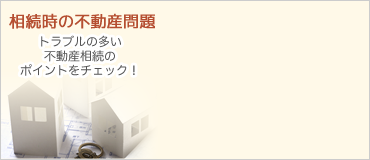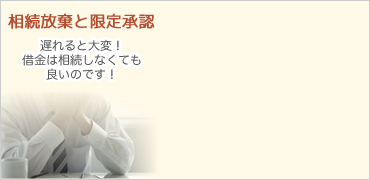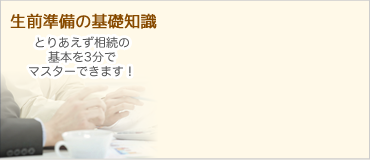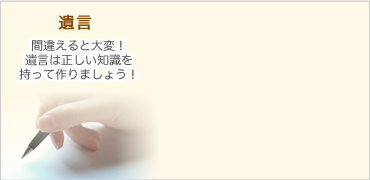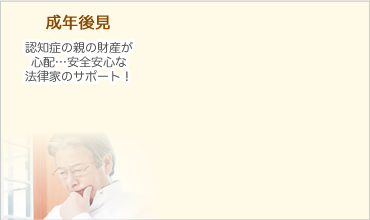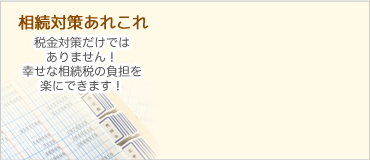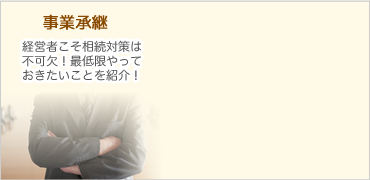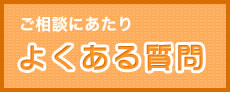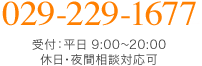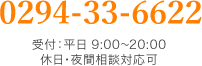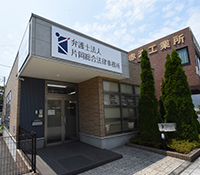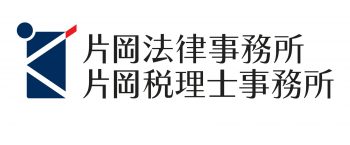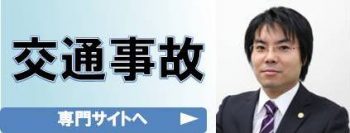【親が認知症になる前に】今すぐ始めるべき3つの対策と家族への効果的なアプローチ
「親が認知症になったら、銀行口座はどうなるんだろう?」「実家の手続きは誰ができるの?」
親御さんが認知症になると、財産管理や不動産の手続き、介護施設の契約などができなくなるリスクがあることをご存知でしょうか。多くの方が「まだ先の話」と考えがちですが、いざという時に家族が困らないためにも、事前の対策が非常に重要です。
今回は、親御さんがお元気なうちに「絶対にやるべき3つのこと」と、ご家族への上手な話の切り出し方について、詳しく解説します。
なぜ「認知症になる前」の対策が必要なのか?
親御さんが認知症になり判断能力が低下すると、ご本人の意思で預金の解約や施設の契約などができなくなります。たとえご家族であっても、勝手に財産を動かすことはできません。
近年、生前贈与や遺言書の作成といった「相続対策」への意識は高まっていますが、「親の介護や認知症」については、つい向き合うのを先延ばしにしてしまう方が少なくありません。
しかし、認知症になってからでは利用できる制度が限られ、手続きも非常に複雑になります。元気なうちだからこそ、スムーズかつ円満に対策を進めることができるのです。
絶対にやるべき3つのこと
対策1:財産管理の今後を話し合い、具体的な制度活用を検討する
まず、親御さんがお元気なうちに、将来の財産管理をどうしていくかを話し合うことが大切です。そのための具体的な制度として「任意後見制度」と「家族信託制度」があります。
任意後見制度(にんいこうけんせいど)
判断能力があるうちに、「もし認知症になったら、この人に財産管理をお願いしたい」という人(任意後見人)を自分で選び、事前に契約を結んでおく制度です。
- 特徴:公証役場で公正証書を作成して契約します。裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」とは異なり、ご自身が信頼する人(親族や弁護士・司法書士などの専門家)を選べます。
- 役割:任意後見人の主な役割は、ご本人の財産を守ることです。施設の契約や預金の管理などを、ご本人に代わってスムーズに行うことができます。
- 注意点:財産を守ることが目的のため、新しい融資や大規模な投資など、財産を積極的に活用・処分する行為は制限されます。
家族信託制度(かぞくしんたくせいど)
ご自身の財産を、信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みです。
- 特徴:任意後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。財産の管理・処分だけでなく、その財産をどのように活用していくかまで、あらかじめ契約で決めておくことができます。
- 具体例:不動産オーナーの方が、将来の認知症に備えて、子供に不動産の管理や必要に応じた売却・買い替えまで任せることができます。
- 注意点:任意後見制度に比べて自由度が高い分、設計が複雑で、専門家への依頼費用など初期コストが高くなる傾向があります。ある程度の資産をお持ちの方に適した制度と言えます。
対策2:遺言書を作成する
判断能力がなくなると、原則として遺言書を作成することはできません。
法律上は、認知症と診断された後でも医師2名以上の立ち会いがあれば作成可能とされていますが、現実的にそのリスクを負って協力してくれる医師はほとんどいません。
また、認知症の傾向が出始めた段階で作成した遺言書は、後になって他の相続人から「作成当時はすでに判断能力がなかったのではないか」と、その有効性を争われるリスクが高まります。
特に、内容が複雑な遺言書ほど無効と判断されやすくなります。相続トラブルを防ぐためにも、心身ともにお元気なうちに、できるだけ早めに作成しておくことが望ましいでしょう。
対策3:財産の洗い出しと情報共有を行う
ご本人が認知症になる前に、どのような財産をどこに所有しているのか、すべて洗い出してリスト化しておくことが非常に重要です。
特に高齢の方の場合、名義変更が済んでいない不動産が後々のトラブルの原因になるケースが少なくありません。また、最近ではネット銀行やネット証券など、ご家族が把握していないデジタル資産が問題になることもあります。
財産の種類や保管場所を一覧にし、ご家族と共有しておくことが不可欠です。
さらに、財産そのものだけでなく、「隣家との土地境界に関する取り決め」や「この土地だけは売りたくない理由」など、ご本人しか知らない情報や想いも、元気なうちに伝えておいてもらいましょう。これらの情報が、将来の円満な相続や無用な紛争の防止に繋がります。
親御さんへ対策の話を切り出すアプローチ方法
「親に財産や相続の話を切り出すのは、どうも気が引ける…」と感じる方は多いでしょう。円滑に話し合いを進めるためのポイントをご紹介します。
1.親御さんの関心事を理解することから始める
お子様が「相続」を心配しているのに対し、親御さんは「これからの自分の生活」に不安を感じていることが多いものです。「誰が面倒を見てくれるのか」「施設にはいつ入るべきか」「お金は足りるのか」など、親御さんが今、最も関心を持っていることを理解し、そこから話を始めるのが良いでしょう。
2.自分の不安を「相談」という形で共有する
親御さんの気持ちに寄り添った上で、「お父さん(お母さん)のことで、実はこんなことが心配なんだ」と、ご自身の気持ちを共有することで、命令ではなく「相談」という形になり、話し合いが進みやすくなります。一方的に「こうしてほしい」と要求するのではなく、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
3.専門家を交える
親子だけでは感情的になってしまい、話が進まないこともあります。そんな時は、第三者である専門家を交えるのが有効です。お互いの気持ちがある程度整理できた段階で、弁護士や司法書士が間に入ることで、客観的な視点から対策の必要性を伝え、具体的な手続きをスムーズに進めることができます。
もし対策しなかったら?「法定後見制度」の課題
もし、事前の対策を何もしないまま認知症になってしまった場合、「法定後見制度」を利用することになります。しかし、この制度は国が推進しているにもかかわらず、いくつかの課題から利用が伸び悩んでいるのが実情です。
- 使い勝手の悪さ:一度後見人が選任されると、ご本人が亡くなるまで、家庭裁判所への定期的な報告(通帳のコピー提出、財産目録の作成など)が義務付けられます。
- 担い手不足と負担の大きさ:この報告義務が大きな手間となり、ご家族にとって精神的・時間的な負担となります。報告を怠ると罰則が科されたり、裁判所が弁護士などの専門家を後見人に選任したりすることもあり、その場合はご本人の財産から報酬を支払う必要があります。
- 財産の減少:専門家が後見人になった場合、継続的に報酬が発生するため、結果として将来相続するはずだった財産が目減りしてしまうことにも繋がります。
このように、認知症になってから利用する法定後見制度は、ご家族にとって大変な面が多いため、やはり元気なうちの対策の方がはるかに負担が軽いと言えるでしょう。
まとめ:後悔しないために、元気なうちから準備を
親御さんが認知症になった時のために、元気なうちから次の3つの対策を講じることが何よりも大切です。
- 財産管理の話し合いと具体的な制度活用(任意後見・家族信託)
- 遺言書の作成
- 財産の洗い出しと情報共有
そして、親御さんとの話し合いにおいては、ご本人の不安や関心事を理解し、ご自身の気持ちも伝えながら、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
当事務所では、認知症になる前の各種対策に関するご相談を承っております。ご家族だけで進めるのが難しいと感じたら、ぜひお気軽に専門家へご相談ください。