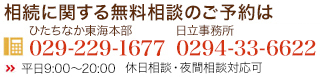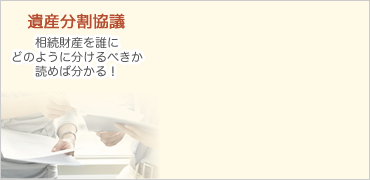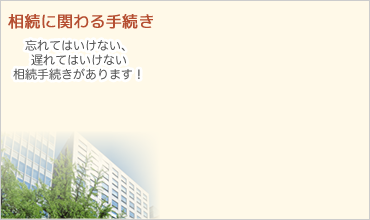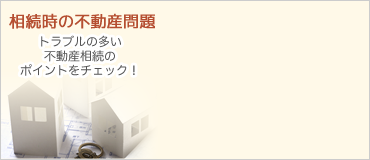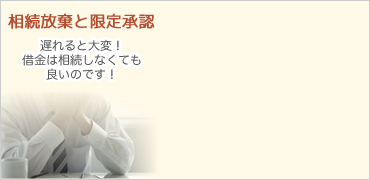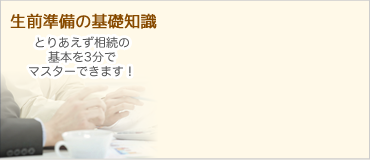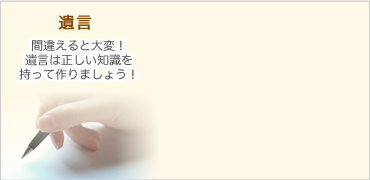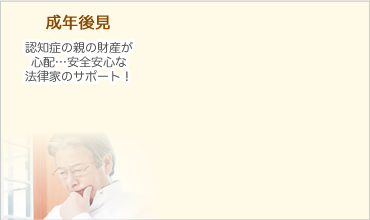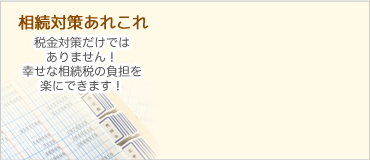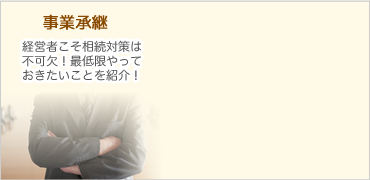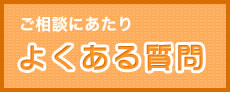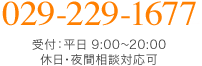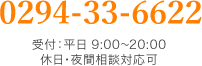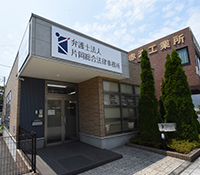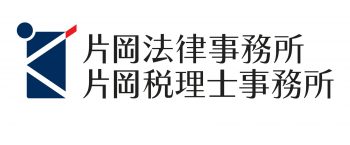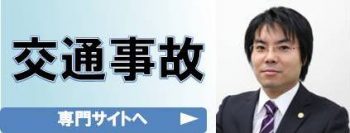【専門家が解説】相続で揉めやすい金融商品3選|知らないと損する対策とは?
近年、資産運用の多様化に伴い、外貨建て商品や未上場株、仮想通貨(暗号資産)といった特殊な金融資産をお持ちの方が増えています。これらの資産は、ご自身の代ではメリットがあっても、いざ相続となると、予期せぬトラブルや負担を相続人に強いる可能性があります。
当事務所のYouTubeチャンネル「今より一歩明るい相続チャンネル」で公開した動画を基に、特に相続トラブルに発展しやすい金融商品を3つ取り上げ、その理由と具体的な対策について詳しく解説します。
1. 外貨建て商品(外国株式、外貨預金など)
まず、相続時にトラブルの火種となりやすいのが、ドルやユーロ、アメリカ株といった外貨建ての商品です。
トラブルになりやすい理由
-
価値の変動
- 日本円と異なり、外貨の価値は日々変動します。そのため、被相続人が亡くなった時点(相続税評価の基準時)と、実際に遺産分割協議を行う時点とで資産価値が大きく変わってしまうことがあります。この価値のズレが、相続人間の不公平感を生み、揉め事の原因となります。
-
手続きの煩雑さ
- 国内の金融機関でも外貨建て商品の相続手続きは複雑になりがちです。特に、海外の金融機関に直接口座を持っている場合、その国の法律に基づいた解約手続きが必要となり、極めて煩雑です。英語での書類準備や国際手続きに詳しい専門家のサポートが不可欠となり、費用もかさみます。少額の資産のために手続きを断念せざるを得ないケースも少なくありません。
-
具体的な対策
-
生前に日本円へ換金する
- 特別な理由がなければ、ご自身が元気なうちに日本円に換えておくのが最もシンプルで確実な対策です。これにより、価値の変動リスクがなくなり、相続人がスムーズに話し合いを進められます。
-
海外資産は国内に移管する
- 海外の金融機関にある資産は、必ず日本の金融機関に移しておくべきです。万が一の際にも、国内の専門家に日本語で相談しながら手続きを進めることができます。
2. 未上場株
次に、証券取引所に上場していない会社の株式、いわゆる「未上場株」も、相続において大きな問題を引き起こす資産です。
トラブルになりやすい理由
-
売却が困難
- 上場株と違い、未上場株には市場価格がありません。買い手を見つけること自体が非常に困難です。さらに、多くの未上場株には「譲渡制限」が付されており、売買には会社の承認が必要となるため、手続きは一層複雑になります。
-
評価と換金の問題
- 税理士などに依頼すれば株の評価額を算出することは可能ですが、評価額がついても買い手がつかない「売るに売れない」状況が頻発します。この株を相続した人は、他の相続人から「評価額分の現金を代わりにほしい」と要求される可能性があります。最悪の場合、他の相続人に支払うためのお金(代償金)を自分で用意しなければならなくなります。
-
納税資金の問題
- 売却できず現金化できないにもかかわらず、相続税は算出された評価額に基づいて課税されます。納税資金が手元にない場合、他の財産を売却したり、借入れをしたりして納税せざるを得ない事態に陥る危険があります。
-
具体的な対策
-
遺言書で承継者を指定する
- 誰が未上場株を相続するのか、遺言書で明確に指定しておくことが最もシンプルで効果的です。例えば、後継者である長男に相続させる代わりに、他の相続人には十分な現預金を渡す、といった配慮をしておくことが重要です。
-
生前の対策を検討する
- ご自身がオーナー経営者である場合などは、専門家と相談の上、計画的に株の評価額を引き下げる対策などを検討することも有効です。
3. 仮想通貨(暗号資産)
近年急速に普及した仮想通貨も、相続においては非常に厄介な資産です。
トラブルになりやすい理由
-
存在を把握できない
- 仮想通貨は特定の金融機関の明細書などで管理されていない場合が多く、本人しかその存在を知らないケースがほとんどです。相続人が資産の存在に気づけず、相続財産から漏れてしまうリスクが非常に高いと言えます。
-
特に注意すべき「税金」の問題
- 仮想通貨の相続は、税金面で極めて大きなリスクを伴います。
- **相続税:**まず、亡くなった時点の価値に対して、他の財産と同様に相続税(最高税率55%)が課税されます。
- **所得税・住民税:**次に、相続した仮想通貨を売却(日本円に換金)すると、その利益に対して所得税・住民税が課税されます。仮想通貨の所得は、現在の税制(2025年8月時点)では「雑所得」として扱われ、給与など他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象です。これにより、税率は最高で55%に達します。
この2つの税金が、それぞれ別のタイミングで課されるため、**極端なケースでは税金の合計額が資産価値を上回る(税率100%超え)**という事態も起こり得ます。例えば、相続税で55%、売却時の所得税・住民税で55%が課税されると、合計で110%となり、手元にお金が残らないどころか、不足分を他の財産で補う必要すら出てくるのです。
具体的な対策
-
情報を家族と共有・記録する
- どの取引所で、どの仮想通貨を保有しているか、ログインIDなどの情報を家族に伝えたり、エンディングノートなどに記録したりしておくことが必須です。
-
遺言書に明記する
- 相続財産として、仮想通貨の情報を遺言書に明確に記載しておくべきです。
-
生前の売却を検討する
- 多額の仮想通貨を保有している場合は、生前に売却して納税(所得税・住民税)を済ませ、残った現預金を相続財産とするのが最も安全な対策です。これにより、税率が100%を超えるという最悪の事態は回避できます。
遺言書だけでは不十分?金融資産の相続で注意すべき点
遺言書を作成していても、新たな問題が発生することがあります。それは、遺言書作成後に新しい金融機関の口座を開設するケースです。
例えば、「A銀行の預金は長男に、B銀行の預金は次男に」と指定した遺言書を作成した後に、NISA口座や新たな証券口座を作ると、その口座の財産は遺言書の指定から漏れてしまいます。結果、その財産について相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要となり、トラブルの原因となります。
これを防ぐためには、遺言書に**「本遺言に記載のないその他の財産は、すべて長男に相続させる」**といった包括的な一文を必ず加えておきましょう。
円満な相続の鍵は「資産のシンプル化」
相続対策は、資産を増やすことだけでなく、「いかにスムーズに次の世代へ引き継ぐか」を考えることが極めて重要です。今回ご紹介したような特殊な金融商品をお持ちの方は、ぜひお元気なうちに対策を講じてください。
残されたご家族が困らないよう、資産をできるだけシンプルで分かりやすい形にしておくこと。それが、円満な相続を実現するための最大の鍵と言えるかもしれません。